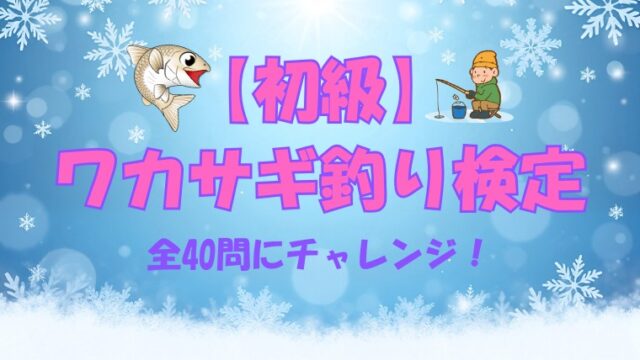誰でも簡単に楽しめる「ワカサギ釣り」。
ファミリーや仲間と、ワイワイ気軽に楽しめるのが魅力です。
ところで、ワカサギの生態についてはご存知でしょうか?
ワカサギ釣りを趣味として続けるのであれば、ワカサギ自体についても知識を深めておきましょう。
記事の最後に理解度をチェックするテストがあるので、ぜひチャレンジしてみてください。

「ワカサギ」の生態

「ワカサギ」とはどんな魚?大きさは?
ワカサギは「キュウリウオ科」に分類されている魚で、シシャモやチカと同じ仲間です。
そう言われてみれば、どことなくシシャモにフォルムが似ていますね。
ワカサギはもともとは海の魚です。
利根川を上ったものが霞ヶ浦で繁殖して、漁師が獲るようになりました。
霞ヶ浦のワカサギを長野県の諏訪湖に放流したら、繁殖に成功。
その採取した卵を全国の湖に配ったことで、ワカサギ釣りが広まりました。
寿命は1年から3年程度で、生まれてから1年未満の個体を「当歳魚」と呼ばれています。
大きさは生息地のエサの量やワカサギ自体の密度によりますが、釣りの対象になるのは7~8cm程度から。
三歳魚になると10cm以上に成長して「デカサギ」と呼ばれ、多くのワカサギフリークを魅了しています。

ワカサギはなにを食べているの?
ワカサギの仔魚は「ワムシ」を食べて成長します。
輪形動物門に属する汽水産のプランクトンです。
海水魚の養殖での稚魚の生き餌として、大規模に養殖されています。
仔魚期を過ぎると、ミジンコ類などを大型動物性プランクトンが主食に。
そのほか、ユスリカの幼虫なども食べて成長します。
サシやブドウ虫、アカムシなどがワカサギ釣りのエサ。
エサを丸ごと食べることもありますが、エサから出ている体液などに誘われてハリにかかるとされています。
生息地はどこ?
0~30℃の広範囲な水温に適応するとされており、生息地は北海道や東北を中心とした東日本に多く分布しています。
基本的に標高の高い山上湖に生息していますが、現在では養殖によって全国さまざまな湖に放流され、九州でもワカサギ釣りが楽しめるなど人気の釣りモノとして定着しています。
アメリカのカリフォルニア州にも生息しているらしいですよ。
ワカサギ釣りを楽しめる湖については、以下のリンクからチェックできます。
産卵期はいつ頃?
ワカサギの産卵期はおよそ1~6月くらいと幅広く、北の地方へいくほど遅くなります。
産卵は湖岸や河川の流れの弱い場所で群れでおこない、サケ科の魚のようにペアで産卵するわけではありません。
オスが先に成熟し、少しずつメスの成熟する割合が増えていき、次第に産卵のピークを迎えます。
どうやって放流しているの?
ワカサギ釣りが盛んな湖を管理している漁協組合では、産卵事業をおこなっています。
獲ったワカサギに卵を産ませた卵をふ化させてから湖に放す「芦ノ湖方式」の開発により、全国でワカサギの釣れるようになりました。
発眼卵のおもな産地としては芦ノ湖をはじめ、網走湖・諏訪湖・八郎潟などが有名。
ビンを用いた人工ふ化機で発眼卵をふ化させて、ビン内の水流によって湖に仔魚が流れ出るようにして放流しています。
下記の動画は、野尻湖漁業協同組合でおこなっている繁殖事業の様子です。
ワカサギが育ちやすい環境とは?
どのダム湖にワカサギを放流しても、同じように定着するとは限りません。
湖の平均水温やエサの条件など、さまざまな要因によって育ち具合が変わってくるのです。
ワカサギがふ化する際の適水温である6~19℃の湖であっても、エサとなるワムシ類の量や大きさなどにも大きく影響されます。
ミジンコやユスリカの幼虫など大きめなエサを食べられるようになると、うまく育ちやすくなるようです。
ただ、幼魚期を乗り切って成長しても、夏場に適水温を大きく上回るような湖の場合、やはり定着が難しくなります。
もっとワカサギについて知りたい!よくある質問
1匹のワカサギあたり、およそ2,000~3,000粒の卵を産むと言われています。
また、ワカサギ1gあたり1,000匹産むとされ、3gのワカサギなら3,000匹の卵を産むわけですね。
ワカサギは学術上では「キュウリウオ科」に分類されており、たとえば鮎が同じ仲間です。
そのほか、シシャモやチカ、シラウオなども同じキュウリウオ科に分類されています。
ワカサギは淡水に住む魚なので、生ではなく加熱して食べましょう。
とても小さい魚なので、そもそも刺身には向いていません
淡水に棲む魚には寄生虫がいる可能性があり、フライや唐揚げなどでしっかりと加熱調理して食べましょう。
ワカサギが1年でどのくらいに成長するかは、環境によって異なります。
エサや栄養の量が大きく影響されるのはもちろん、放流量が多くワカサギの密度が高めれば、エサの取り合いになって成長が鈍化します。
逆に、湖の大きさに対して放流量が少なければ密度が低くなり、エサに不自由することなく成長が早くなるわけです。
ワカサギは流れのある川には好んで棲みません。
ただ、北海道の網走湖では産卵のため海へ下り、生まれたワカサギが網走川を遡って戻ってくるので、ある程度の遊泳力はあるようです。
とはいえ、一般的には湖などの止水域を好んで棲息する魚である、と理解しておけばよいでしょう。
ワカサギ釣りのシーズンは9~10月に解禁し、翌年の春ごろまで楽しめるの一般的ですが、通年ワカサギ釣りを楽しめる湖もあります。
たとえば、神奈川県の芦ノ湖では解禁期間を3月2日から12月14日までと定めており、夏でもワカサギを楽しめます。
また、長野県の木崎湖には禁漁期間の設定がなく、1年を通じてワカサギ釣りが可能です。
ワカサギの時期や解禁については、以下の記事でも詳しく取り上げています。
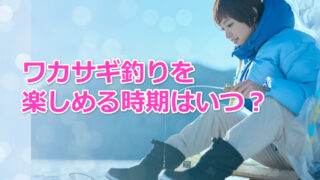
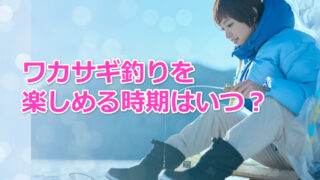
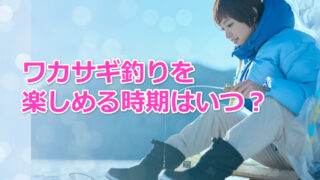
江戸時代に霞ヶ浦の北にある麻生の藩主が、徳川11代将軍徳川家斉へ年賀に参上する際に串焼きのワカサギを献上していたことに由来しているとされています。
将軍家御用達の魚だから「御公儀の魚」、つまり「公魚」というわけですね。
【まとめ】ワカサギの生態の理解度テスト
元々は東日本を中心に生息していたワカサギ。
今では各漁協組合の放流事業によって、関西や九州など全国でワカサギ釣りを楽しめるようになりました。
よく行くフィールドの発眼卵が、どこ産なのかを知っておくのも楽しそうですね。
ワカサギ釣りは船宿さんで道具をレンタルでき、初心者向けのワカサギ釣りツアーも開催されているなど、女性や子どもはもちろん誰でも手軽にはじめられます。
安価な「ワカサギ釣りセット」も販売されているので、ワカサギ釣りに興味があれば以下の記事もぜひチェックしてみてくださいね。



ワカサギ釣りは、誰でも手軽に楽しめるのが魅力です。とはいえ、それなりに道具は必要で、なにを揃えたらよいのかわからない場合も。釣り方にもコツがあります。 以下の記事では、初心者向けに道具・釣り場・釣り方などについて解説しています。ワカサギ釣りに興味があれば、ぜひ読んでみてください。